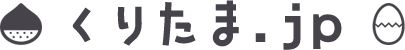Web上で文章を書くWebライターの仕事。
本稿では、Webライティングの基礎やSEOとの関係性を理解し、上手く書くための具体的なコツや注意点を把握でき、Webライターとしての一歩を踏み出すための内容をまとめていきます。
Webライティングとは何か
Webライティングとは、Webサイトに掲載する文章を作成するスキル全体を指します。具体的には、ブログ記事、企業のWebサイトのコンテンツ、商品の紹介ページ(LP)、メールマガジンなど、インターネット上で読まれるあらゆる文章を作成する作業が含まれます。
書籍や雑誌などの紙媒体のライティングと大きく異なるのは、単に読みやすい文章を書くだけでなく、Googleなどの検索エンジンに評価され、上位表示(検索結果の上の方に表示されること)されるための知識も求められるという点です。
つまり、「検索エンジン」と「読者」の双方に向けて書く必要があることが、Webライティングの最大の特徴です。
紙媒体では読者が自ら本を選ぶのに対し、Webでは読者は検索エンジンを介して記事にたどり着くため、Webライターには読み手が離脱しないような画面構成や情報の提示方法の工夫が求められます。
SEOライティングとの関係
Webライティングを語る上で、SEOライティングの知識は欠かせません。
SEOとは、Search Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略語であり、Googleなどの検索エンジンで特定のキーワードを検索した際に、自分の書いた記事をできるだけ上位に表示させるための施策全般を意味します。Webライティングの多くは、このSEOの考え方に基づいて記事を作成することが求められるため、実質的にWebライティングはSEOライティングと深く関わっていると考えて差し支えありません。
SEOライティングでは、読者の検索意図(何を知りたくて検索したのか)を深く理解し、その答えとなる質の高い情報を提供することが最も重要となります。具体的には、単にキーワードを詰め込むのではなく、記事のタイトルや見出しにキーワードを自然に含めること、読者が知りたい情報を網羅的に提供すること、そして読み手が求めている結論を迅速に提示することなどが、SEO効果を高めるコツとなります。
また、「網羅性」も重要であり、検索結果の上位に表示されている複数の記事が扱っているトピックを、自分の記事でもカバーすることが求められます。
最近はChatGPTやGeminiなど生成AIが台頭してきており、SEOのあり方も変化していますが、読者にとって有益な情報をわかりやすくまとめるという基本的な考え方は引き続き重要です。引き続き、網羅的でわかりやすくオリジナルな要素のある記事を心がけるようにしましょう。
Webライティングの2つの型

Webライティングは、その目的によって大きく2つの型に分けられます。プロのWebライターとして活動する際には、クライアントの要望がどちらの型に該当するかを瞬時に判断することが求められます。
1. 読者の行動を促す型(セールスライティング・LPライティング)
この型は、商品の購入、サービスの申し込み、資料請求、会員登録など、読者に具体的な行動を起こしてもらうことを目的としたライティングです。
たとえば、ECサイトの商品説明文やランディングページ(LP)、広告文などがこれにあたります。
セールスライティングでは、読者の悩みや欲求に強く訴えかけるベネフィット(読者が得られる未来)の提示が重要です。商品の特徴ではなく、「その商品を使うことで読者の生活がどう良くなるか」という視点で書きます。
また、行動へのハードルを下げる工夫(限定性、保証など)を凝らし、読者を最終的なコンバージョン(目標達成)へと誘導する明確な流れ(導線)が必要です。
AIが台頭してきても、読者に刺さるフレーズづくりは引き続き重要です。
2. 読者の疑問を解決する型(コンテンツライティング・SEOライティング)
この型は、読者が抱える疑問や課題を解決し、有益な情報を提供することを目的としたライティングです。ブログ記事、企業のオウンドメディア記事、ニュース記事などが該当します。
コンテンツライティングの役割は、読者にとっての「辞書」や「教科書」となることです。信頼性の高い情報をわかりやすく整理し、読者の理解を深めることを最優先とします。そして、検索エンジンでの評価(SEO)を高めて、サイト全体への集客を狙うのが主な目的となります。
Webライターが副業や本業で主に担当するのは、この「読者の疑問を解決する型」が多いです。
Webライティングにおける、書く手順とポイント
質の高いWeb記事を作成するためには、プロとしてしっかりとした手順を踏むことが重要になります。この手順は、クライアントワークにおける品質の安定と納期の厳守にも直結します。
記事執筆の基本的な5つのステップを紹介します。
手順1:テーマの理解とキーワード選定
まず、クライアントから指定されたテーマやキーワードについて、読者が何を知りたいのかリサーチして深く理解することから始めます。
検索してヒットする記事やSNSでの口コミ、時にはユーザーインタビューを実施するなどして、情報収集していきます。できるだけ一次情報やファクトデータを収集することで、説得力のある記事につながります。
リサーチ後、「誰に向けて」「何のために」「何を解決する記事か」という記事の目的やターゲットを明確に設定します。
手順2:構成(アウトライン)の作成
次に、記事全体の設計図として構成案を作成します。見出し(H2, H3, H4)の階層構造と、それぞれの見出しでどのような内容(情報)を、どのくらいのボリュームで書くかを具体的に決めます。
この際、読者の疑問が上から順に、漏れなく解決されていくような論理的な流れを意識することがコツです。
特に、記事の導入部分では読者の興味を引きつけ、記事のベネフィットを伝えることが重要です。いきなり本文を書き始めるのではなく、この構成案をクライアントに確認してもらうことで、手戻りを防ぎ、効率的に作業を進めることができます。
手順3:情報収集と素材の準備
作成した構成案に沿って、記事に記載する情報の裏付けや具体的なデータを集めます。
信頼性の低い個人のブログではなく、公的機関や専門家の信頼できるソースを参考にすることが重要です。
特に、統計データや専門的な見解を引用する際は、情報が最新であるかどうかを必ず確認します。また、統計のようなデータだけでなく、個人のN=1の体験談やリアルな声を収集することでより具体性のある内容となります。
情報を集めたら、自分の言葉で要約し、必ず出典(参考情報)をメモしておきます。間違った情報を書かないように細心の注意を払う必要があります。
手順4:執筆(本文の作成)
情報収集が終わったら、構成案と集めた情報をもとに本文を執筆します。
文章を書く際は、結論から先に述べる(PREP法:結論 →理由→具体例→結論)など、文章の型を意識し、一文一文を短く、初心者でもわかるように専門用語を使いすぎないように書くことがポイントです。「です」「ます」が連続して続かないよう、文末表現に変化を持たせるよう意識しましょう。
また、読者が飽きずに読み進められるよう、適度な改行や画像、図解の挿入を意識しながら執筆します(実際の挿入作業はWebデザイナーや編集者が行うことが多いですが、ライターは挿入指示まで行います)。
手順5:推敲・校正
記事を書き終えたら、誤字脱字、文法ミスがないかをチェックする校正と、読者目線で「本当にわかりやすいか」「説明に矛盾はないか」を客観的に見直す推敲を行います。
執筆直後ではなく、時間を置いてから読み直すと、ミスに気づきやすくなります。
特に「てにをは」(助詞)の間違いや、主語と述語がねじれていないかなどを注意深く確認することが重要です。この段階で、読者にとって価値のある情報が不足していないか、記事の冒頭で約束した内容(ベネフィット)がしっかり提供できているかという視点からもチェックを行います。
Webライティングで文章が書けない原因

「構成案は作ったのに、いざ本文を書こうとすると手が止まる」という悩みは初心者によくある壁です。これは、主に以下の3つの原因が考えられます。
1. 読者の意図が不明確である
誰に向けて、何を伝え、どうなってほしいかという記事のゴールが曖昧なまま書き始めている状態が原因です。
この状態だと、文章の一貫性がなくなり、結局何を言いたいのかが伝わりにくくなります。対策として、執筆を始める前に、関連したテーマやキーワードで検索エンジンやSNSで検索し直してユーザーのインサイトを再確認しましょう。読者が本当に知りたい核心は何か、その疑問の背景にある悩みまで深く掘り下げることが重要です。
2. インプット(情報収集)が不足している
書くべき内容の知識や、具体的に何を説明すれば読者が納得するかという情報量が足りていないことが原因です。
情報量が不足していると、抽象的な表現が多くなり、読者に具体的なイメージを伝えられません。
対策としては、もう一度、構成案の各見出しに必要な情報が揃っているかを確認し、不足していると感じたら、信頼できるソースから情報を追加で集める必要があります。この情報収集の質が、記事の説得力を大きく左右します。
3. 一文が長すぎる、論理の飛躍がある
完璧な文章を一発で書こうとしすぎたり、複雑な情報を無理に一文に詰め込もうとしたりしていることが原因です。
長すぎる文章は読み手が途中で離脱する原因となります。対策として、「一文一義」(一つの文には一つの情報だけ)を徹底し、文章を短く区切ります。
また、文章作成において論理的な流れを意識し、前の文と後の文がスムーズにつながっているか、話が飛躍していないかを常に確認することも大切です。
Webライティングが上達になるコツ
Webライティングは、才能ではなくスキルであり、意識的に訓練すれば誰でも上達できます。上達のスピードを上げるには、効率の良い学習方法を取り入れることが重要です。
上手くなるコツ1:良い文章を「真似る」
Webライティングのプロが書いた上位表示されている記事を読み込み、「なぜこの文章は読みやすいのか」「なぜここでこの情報が必要なのか」を分析するコツがあります。
ただ読むだけでなく、記事の構成、見出しのつけ方、文章のリズムや使われている比喩表現などを「型」として自分のものにする意識で取り組みましょう。
たとえば、良い文章を写経(書き写すこと)したり、上位記事の構成を自分で一度完全に再現してみたりするのが有効です。
この「真似る」作業は、インプットとアウトプットを兼ねた非常に効果的なトレーニングになります。
上手くなるコツ2:常に読者目線を意識する
記事を書く目的は、自分の書きたいことを書くことではなく、読者の問題を解決することです。
常に「これは読者に伝わるだろうか」「この情報は読者が求めているものだろうか」と自問自答します。特に、文章を書き終えた後に、記事のターゲットである読者になりきって、違和感なくスムーズに読めるかどうかをチェックすることが重要です。
専門用語を使う際は、必ず()書きで初心者にもわかる簡単な言葉で言い換えや補足を加えるなど、読者への配慮が必要です。
上手くなるコツ3:フィードバックをもらう機会を作る
自分の書いた文章を客観視するのは難しいため、クライアントやライティング仲間から具体的なフィードバックをもらい、修正と改善を繰り返すことで、成長速度が格段に上がります。
フィードバックは、「修正するべき箇所」だけでなく、「評価された良い点」も把握することが上達のモチベーション維持につながります。添削サービスを利用したり、ライティングを学べる講座で指導を受けたりすることも、効率的な上達方法の一つです。
初心者は案件をこなす中で、クライアントからのフィードバックを素直に受け止め、次回に活かす姿勢がプロには求められます。フィードバックは耳が痛くなるような瞬間も時にはありますが、どれだけ素直に受け入れて改善できるかが上達の鍵となります。
Webライティングの書き方の注意点

読者にストレスなく情報を伝え、検索エンジンからも評価される記事にするために、必ず守るべき注意点があります。
1. 著作権・引用のルールを守る
他のサイトの文章や画像を無断でコピー&ペーストすることは、著作権の侵害にあたります。
これは法律違反であり、プロのライターとして絶対にやってはいけないことです。他者の文章を参照する場合は、自分の言葉で要約して書くか、そのまま引用する必要がある場合は、引用符(「」や<blockquote>)を使い、出典(参考情報)を明記します。
また、画像を使用する際も、必ず著作権フリーの素材を利用するか、クライアントに提供されたものを使用しましょう。
2. 記事の信頼性を高める
特に医療、金融、法律など人々の人生に影響を与えるテーマでは、情報の正確性と信頼性が極めて重要です(GoogleのE-E-A-T評価にも関わります)。E-E-A-Tとは、Experience(経験)、Expertise(専門性)、Authoritativeness(権威性)、Trustworthiness(信頼性)の頭文字をとったもので、これらの要素が高いほど、Googleに評価されやすくなります。
情報源として、公的機関(厚生労働省、消費者庁など)や専門家の論文・報告書など、信頼できる機関の参考情報を記載し、記事の信頼性を高めましょう。
3. 推敲と校正を徹底する
誤字脱字が多い記事は、読者にストレスを与えるだけでなく、記事全体の信頼性を大きく損ないます。執筆後に必ず音読してリズムや不自然な箇所をチェックします。チェックツールやWordの校正機能などを活用して、ミスを見落とさないように徹底しましょう。
特に、数字や固有名詞、日付などの事実は何度も確認し、クライアントから指定されたレギュレーション(表記ルール)を遵守しているかどうかも、校正の段階で厳しくチェックすることがプロとしての責務です。
Webライティングを学ぶデジハリ
Webライターとして活躍し、安定して副業や本業で稼ぐためには、基礎から応用まで体系的にスキルを学ぶことが最も効率的です。
Webライティングは独学でも始められますが、質の高い案件を獲得し、初心者の段階でつまずかないためには、プロから直接指導を受けるのが近道です。
Webライターの仕事は、文章力だけでなく、クライアントとのコミュニケーション能力や、安定して初心者 案件を獲得するための営業力も求められます。独学で学ぶ際は、まず本を何冊か読んで基礎知識を得ることも大切ですが、プロのスキルを短期間で身につけたいなら、デジハリ・オンラインスクールのWebライター養成講座がおすすめです。
デジハリ・オンラインスクールでは、Webライティングの基礎から、SEOの知識、そして実際に案件を獲得して納品するまでの実践的な流れを学ぶことができます。プロの指導のもとで実践的なスキルを習得することで、市場価値の高いライターになることを目指せます。
講座を修了しても、Webライターとして活動するのに資格は必須ではありませんが、体系的な知識を身につけることは、クライアントからの信頼を得る上で大きな武器となります。
まとめ
この記事では、Webライティングの基礎から、上手く書くための具体的な手順、そして上達のコツや注意点について解説しました。Webライティングは、SEOを意識し、検索エンジンと読者の双方に向けて書くスキルです。手順は、「キーワード選定」→「構成作成」→「情報収集」→「執筆」→「推敲」の5ステップを必ず守りましょう。
また、上達のコツは、良い文章の真似(分析)と、常に読者目線を意識することです。
Webライティングのスキルは、Web業界以外でも、メール作成、企画書作成などあらゆるビジネスシーンで役立つ汎用性の高いスキルです。このスキルを身につけて、副業やキャリアアップにつなげてみませんか。デジハリ・オンラインスクールのWebライター養成講座では、プロのWebライターとして活躍するために必要な実践的なスキルを体系的に学べます。


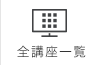
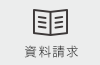
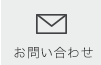
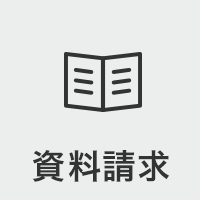











 Webデザイン
Webデザイン




 3DCG・映像
3DCG・映像





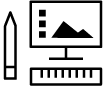 グラフィックデザイン
グラフィックデザイン
 Webマーケティング
Webマーケティング
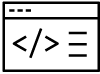 Webプログラミング
Webプログラミング
 アナログスキル
アナログスキル

 その他
その他