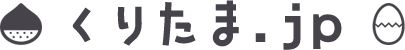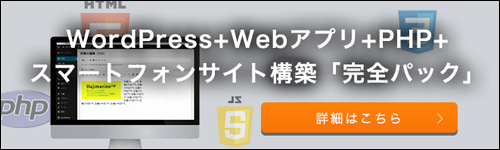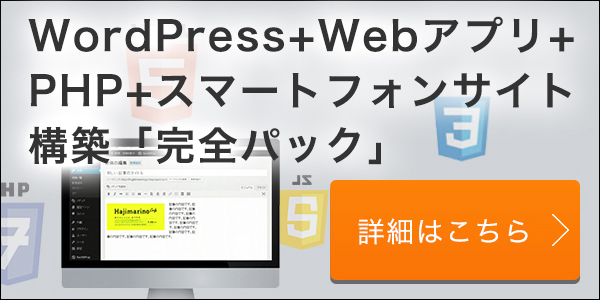スマートフォンアプリやWebサイトを利用する際、「使いやすい」「心地よい」と感じた経験はありませんか?
その背景には、優れたUXデザインが存在しています。デジタルサービスが生活に欠かせない存在となった現代において、UXデザインの重要性はますます高まっている状況です。
本記事では、UXデザインの基本概念から実践的な手法まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
これからUXデザインを学び、キャリアに活かしたい方はぜひ参考にしてください。
UXデザインとは?
UXデザインとは、「User Experience Design(ユーザーエクスペリエンスデザイン)」の略称で、製品やサービスを利用する際にユーザーが得る体験全体を設計することを指します。
単に見た目の美しさや操作性だけでなく、ユーザーがサービスと接する前から後まで、あらゆる接点における感情や満足度を含めた総合的な体験をデザインする考え方です。
例えば、ECサイトであれば、商品を探しやすいか、購入手続きはスムーズか、商品到着後のサポートは充実しているかといった、一連の体験すべてがUXデザインの対象となります。
“UXデザインを作る”と表現される場合もあるが実際に作ることはできない
実務の現場では「UXデザインを作る」という表現を耳にすることがありますが、厳密に言えばUX(ユーザー体験)そのものを直接作り出すことはできません。
なぜなら、体験はユーザー個人の感じ方や背景、状況によって異なるものだからです。デザイナーができることは、優れた体験が生まれるような「環境」や「仕組み」を設計することに限られます。
つまり、インターフェースの使いやすさや情報の見つけやすさ、サービスの流れなどを最適化することで、結果的に良い体験をユーザーに提供できるよう導くわけです。
UXデザインとは、体験そのものではなく、体験を生み出すための設計プロセス全体を意味していると理解しておくと良いでしょう。
UXデザインの例
身の回りには、優れたUXデザインによって快適な体験を提供しているサービスが数多く存在しています。ここでは、私たちが日常的に利用しているサービスの中から、UXデザインの好例を2つ紹介していきます。
オンラインショッピングサイトの購入体験
大手ECサイトでは、商品検索から購入完了まで、ユーザーがストレスなく買い物できるよう細部まで設計されています。
例えば、過去の閲覧履歴に基づいたおすすめ商品の表示、ワンクリックで購入できる機能、配送状況のリアルタイム通知など、ユーザーの手間を減らす工夫が随所に施されているのが特徴です。さらに、購入後のレビュー投稿を促す仕組みや、返品手続きの簡素化なども、購入後の体験を向上させるUXデザインの一部となっています。
これらの積み重ねによって、ユーザーは「また利用したい」という気持ちになり、サービスへのロイヤリティが高まっていくわけです。
音楽ストリーミングサービスの利用体験
SpotifyやApple Musicなどの音楽ストリーミングサービスでは、膨大な楽曲の中から好みの音楽を見つけやすくする工夫が凝らされています。
ユーザーの聴取履歴や好みを分析して、パーソナライズされたプレイリストを自動生成する機能は、探す手間を省きながら新しい音楽との出会いも提供してくれます。また、オフライン再生機能やシームレスなデバイス間の連携により、場所や状況を選ばず音楽を楽しめる環境が整えられている点も優れたUXデザインの例です。
アプリを開いた瞬間から、直感的に操作でき、気分やシーンに合わせた音楽にすぐアクセスできる設計は、ユーザーに心地よい体験を継続的に提供しています。
UXデザインとUIデザインの違い

UXデザインとUIデザインは密接に関連していますが、それぞれ異なる役割を担っています。
UIデザイン(User Interface Design)は、ユーザーが直接触れる画面やボタン、アイコンなどの視覚的要素を設計する領域を指します。
一方、UXデザインはUIデザインを含むより広範な概念で、ユーザーがサービス全体を通じて得る体験すべてを対象としている点が大きな違いです。
例えば、美しく整ったボタンのデザインはUIデザインの成果ですが、そのボタンをどこに配置すれば使いやすいか、ボタンを押した後にどんな反応があればユーザーは安心できるかを考えるのがUXデザインの領域になります。
つまり、UIデザインは「見た目と操作性」に焦点を当てているのに対し、UXデザインは「ユーザーの目的達成と満足度」という、より本質的な価値の提供を目指しているわけです。両者は車の両輪のような関係で、優れたUIがあっても全体の体験設計が不十分であれば良いUXは生まれません。逆に、素晴らしいUX設計があっても、UIが使いにくければユーザーは満足できないでしょう。
UXデザインにおけるユーザーの消費傾向ごとの重要性
現代の消費者行動は、単に商品やサービスの機能だけでなく、そこで得られる体験に価値を見出す傾向が強まっています。
特にデジタルネイティブ世代を中心に、使いやすさや心地よさといった感覚的な要素が購買決定の重要な要因となっているのが実情です。同じ機能を持つ製品が複数ある場合、ユーザーは使用時のストレスが少なく、満足度の高い体験を提供してくれるものを選ぶようになりました。
この変化により、企業にとってUXデザインへの投資は差別化の重要な戦略となっています。さらに、サブスクリプションモデルが普及した現在では、継続利用を促すためのUXデザインの役割はより一層重要になっています。
初回利用時の満足度だけでなく、長期的に使い続けたいと思える体験を設計することが、ビジネスの成功を左右する時代になったと言えるでしょう。
UXを構成する要素
UXを構成する要素は多岐にわたりますが、主に以下の5つの層から成り立っています。最も基礎となるのが「戦略」の層で、ビジネスゴールとユーザーニーズを定義します。
次に「要件」の層では、必要な機能や情報を明確化していきます。「構造」の層では、情報をどう整理し、ユーザーがどのような流れでサービスを利用するかを設計します。さらに「骨格」の層で、具体的な画面レイアウトやナビゲーションの配置を決定し、最上位の「表層」でビジュアルデザインを仕上げていく形です。
良いUXデザインとは、これらすべての層が調和し、ユーザーにとって価値ある体験を提供できている状態を指します。具体的には、ユーザーが目的を達成しやすく、使用中にストレスを感じず、むしろ楽しさや満足感を得られるような設計が理想的です。
また、アクセシビリティの観点から、あらゆるユーザーが利用できる配慮がなされていること、一貫性のある操作感で迷わず使えること、エラーが起きにくく、起きた場合も適切なフィードバックがあることなども重要な要素となります。
UXを設計・改善するためのプロセス
UXデザインを効果的に進めるには、体系的なプロセスに従って段階的に取り組むことが重要になります。ここでは、実務で広く活用されている5つのステップを紹介していきます。
①ユーザーの課題を見つける
UXデザインの第一歩は、ユーザーが抱えている課題やニーズを正確に把握することから始まります。
ユーザーインタビューやアンケート調査、行動観察などの手法を用いて、実際のユーザーの声や行動を収集していきます。
この段階で重要なのは、先入観や仮説に囚われず、客観的にユーザーの実態を理解する姿勢です。また、アクセス解析ツールを使ってユーザーの行動データを分析し、離脱が多いポイントや使われていない機能を特定することも有効な手段です。
②ペルソナやカスタマージャーニーマップを作成する
ユーザーの課題が明確になったら、次は具体的なユーザー像を描くペルソナを作成します。
ペルソナとは、年齢や職業、ライフスタイル、価値観などを設定した架空のユーザー像で、チーム全体で共通のターゲット像を持つために作成されます。単なる属性情報だけでなく、その人の行動パターンや目標、悩みなども詳しく設定することで、よりリアルなユーザー像が描けるでしょう。
さらに、カスタマージャーニーマップを作成することで、ユーザーがサービスと出会う前から利用後までの一連の体験を可視化できます。
③実際に設計を行う
ペルソナとカスタマージャーニーマップが完成したら、具体的な設計作業に入ります。
まずはワイヤーフレームと呼ばれる簡易的な画面設計図を作成し、情報の配置やナビゲーションの流れを検討していきます。この段階では細かいデザインにこだわらず、構造や機能面に集中することがポイントです。ワイヤーフレームで大枠が固まったら、プロトタイプと呼ばれる試作版を作成します。
④ユーザビリティテストなどで評価を行う
プロトタイプが完成したら、実際のユーザーに使ってもらうユーザビリティテストを実施します。
テストでは、ユーザーに特定のタスクを実行してもらい、その過程を観察することで、想定通りに使えているか、どこでつまずいているかを把握します。テスト結果から得られた課題や改善点をもとに、設計を修正していきます。
⑤PDCAサイクルで回す
サービスをリリースした後も、UXデザインの改善は継続的に行う必要があります。
Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Act(改善)のPDCAサイクルを回し続けることで、常にユーザーにとって最適な体験を提供できる状態を維持します。リリース後のユーザー行動データやフィードバックを定期的に分析し、新たな課題や改善機会を見つけていきましょう。
UXデザインを用いる”UXデザイナー”とはどんな職業?

UXデザイナーとは、ユーザー体験の設計と改善を専門とする職業です。ユーザー調査から課題発見、設計、評価まで、UXデザインの一連のプロセスを担当し、ユーザーにとって価値あるサービスを生み出す役割を果たします。デジタルサービスの普及に伴い、企業におけるUXデザイナーの需要は年々高まっている状況です。
関連記事:UI/UXデザイナーの仕事内容と年収は?未経験からなるためのステップを解説
主な仕事内容
UXデザイナーの仕事は多岐にわたりますが、主要な業務としてまず挙げられるのがユーザーリサーチです。
インタビューやアンケート、行動観察などを通じてユーザーのニーズや課題を明らかにし、データに基づいた設計の基盤を作ります。
次に重要なのが情報設計で、サービス内の情報をどのように整理し、ユーザーが目的を達成しやすい導線を作るかを考える作業です。
また、ワイヤーフレームやプロトタイプの作成も重要な業務で、設計したアイデアを具体的な形にして関係者と共有します。
さらに、ユーザビリティテストの計画・実施も担当し、設計の妥当性を検証していきます。プロジェクトによっては、UIデザイナーやエンジニア、マーケティング担当者など、様々な職種とコミュニケーションを取りながら協働することも多いため、コミュニケーション能力も求められる職業と言えるでしょう。
UXデザインを外注する際に知っておくべきこと
自社にUXデザインの専門知識を持つ人材がいない場合、外部のUXデザイン会社に依頼することも有効な選択肢となります。ここでは、外注する際に押さえておきたいポイントを解説していきます。
UXデザイン会社に依頼できること
UXデザイン会社では、プロジェクトの規模や目的に応じて様々なサービスを提供しています。
代表的なものとして、ユーザー調査の実施とレポート作成があり、専門的な手法を用いて客観的なユーザーインサイトを抽出してもらえます。また、既存サービスのUX評価と改善提案も依頼できるため、現状の課題を専門家の視点で洗い出すことが可能です。
新規サービスの企画段階から参画してもらい、コンセプト設計からプロトタイプ作成まで一貫して依頼することもできます。さらに、ワークショップの開催を通じて、社内チームにUXデザインの考え方を浸透させるような教育的な支援を受けることも可能です。
外注する前に自社の課題を明確にする
UXデザイン会社に依頼する前に、まず自社が解決したい課題や達成したい目標を明確にしておくことが成功の鍵となります。
漠然と「使いやすくしたい」という依頼では、期待する成果が得られない可能性が高くなってしまいます。
例えば、「新規ユーザーの離脱率を下げたい」「購入完了率を向上させたい」といった具体的な課題を設定しましょう。また、プロジェクトの予算や期間、社内の体制なども事前に整理しておくことで、現実的な提案を受けやすくなります。
UXデザイン会社を選ぶ際のコツ
適切なUXデザイン会社を選ぶには、いくつかのポイントを押さえておく必要があります。
まず重要なのが実績の確認で、自社の業界や類似プロジェクトの経験があるかをチェックしましょう。会社のWebサイトで公開されている事例を見ることで、デザインの質や得意分野を判断できます。次に、提案内容の具体性も重要な判断基準です。
初回の打ち合わせや提案書で、課題に対してどのようなアプローチを取るのか、具体的なプロセスが示されているかを確認してください。また、コミュニケーションの取りやすさも長期的な協業では重要な要素となります。さらに、料金体系の透明性や、プロジェクト後のサポート体制なども確認しておくことで、後々のトラブルを避けることができます。
UXデザインを独学で勉強する方法

UXデザインは専門的な知識が必要ですが、独学でも十分に学ぶことが可能です。ここでは、効果的な学習方法を3つ紹介していきます。
書籍やオンライン記事で基礎知識を学ぶ
UXデザインの学習において、まず取り組むべきなのが基礎知識の習得です。
入門書としては、「UXデザインの教科書」や「誰のためのデザイン?」といった定番書籍が理解を深めるのに役立ちます。
これらの書籍では、UXデザインの考え方や基本的なプロセス、実践的な手法などが体系的に解説されています。
また、インターネット上にも質の高い記事やブログが数多く公開されており、無料で学習できる環境が整っている点も魅力です。海外の情報にも目を向けると、Nielsen Norman GroupやUX Collectiveといった専門サイトで、最新のUXデザイントレンドや調査結果を学ぶことができます。
オンライン学習プラットフォームの活用
体系的にUXデザインを学びたい場合は、オンライン学習プラットフォームの活用が効果的です。
UdemyやCourseraなどのプラットフォームでは、UXデザインに関する様々なコースが提供されており、動画講義を通じて実践的なスキルを身につけることができます。特に、実際の事例を用いたケーススタディや、ツールの使い方を学べる実習型のコースは、実務に直結する知識を得られる点で価値があります。
また、多くのプラットフォームでは受講者同士のコミュニティがあり、学習の疑問点を質問したり、他の学習者の作品からインスピレーションを得たりすることも可能です。
実際にデザインを作成してポートフォリオを構築
知識を学ぶだけでなく、実際に手を動かしてデザインを作成することが、UXデザインスキル向上の最も効果的な方法です。
既存のサービスを分析し、改善案を考えてプロトタイプを作成する練習から始めてみましょう。FigmaやAdobe XDといった無料で使えるデザインツールを活用すれば、初心者でも本格的なプロトタイプ作成が可能です。
また、架空のプロジェクトを設定し、ユーザーリサーチからプロトタイプ作成まで一連のプロセスを実践することで、包括的なスキルが身につきます。作成した作品はポートフォリオとしてまとめ、就職活動や案件獲得の際にアピール材料として活用できます。
UXデザインに役立つ資格
UXデザインの学習において、資格取得は知識を体系的に整理し、スキルを証明する有効な手段となります。ここでは、UXデザイナーを目指す方におすすめの3つの資格を紹介します。
人間中心設計専門家
人間中心設計専門家は、特定非営利活動法人人間中心設計推進機構(HCD-Net)が認定する資格で、UXデザインの専門性を証明する国内有数の認定制度です。人間中心設計の理念と手法を理解し、実務に活用できる能力を持つことを証明できます。
資格は「スペシャリスト」と「専門家」の2段階に分かれており、スペシャリストは基礎的な知識と実務経験が求められ、専門家はより高度な実践力が必要となります。試験では、人間中心設計プロセスの理解や、ユーザビリティ評価の手法、プロジェクトマネジメントなどが問われます。
ウェブデザイン技能検定
ウェブデザイン技能検定は、厚生労働省が認定する国家資格で、Webサイト制作に関する幅広い知識とスキルを証明できます。
1級から3級まであり、3級は基礎的な知識から始められるため、初心者でも挑戦しやすい資格です。
試験内容には、Webデザインの基礎知識に加えて、ユーザビリティやアクセシビリティに関する項目も含まれており、UXデザインの基礎となる考え方を学べます。HTML/CSSなどの技術的な知識も問われるため、UIデザインとの橋渡しとなる知識も同時に習得できる点が特徴です。
Google UX Design Professional Certificate
Google UX Design Professional Certificateは、Courseraで提供されているGoogleによる認定プログラムです。
全7コースから構成されており、UXデザインの基礎から実践的なスキルまで、体系的に学ぶことができます。プログラムでは、ユーザーリサーチ、ワイヤーフレーム作成、プロトタイピング、ユーザビリティテストといったUXデザインの主要なプロセスを、実際のプロジェクトを通じて習得していきます。
修了時には、ポートフォリオに掲載できる複数のプロジェクト作品が完成している点も魅力的です。
UXデザインに関するQ&A

UXデザイナーとWebデザイナーの違いは?
UXデザイナーとWebデザイナーは、仕事内容や求められるスキルに違いがあります。
Webデザイナーは主に、Webサイトの視覚的なデザインやレイアウトを担当し、HTML/CSSなどの技術を用いて美しく機能的なWebページを作成することが主な仕事です。
一方、UXデザイナーは、ユーザーがサービス全体を通じて得る体験を設計する役割を担っており、ユーザーリサーチや情報設計、プロトタイピングなど、より上流の工程から関わります。Webデザイナーが「どう見せるか」に重点を置くのに対し、UXデザイナーは「どう使ってもらうか」「どんな体験を提供するか」という視点で仕事を進める点が大きな違いです。
UXデザイナーに向いている人の特徴は?
UXデザイナーに向いているのは、まず人間の行動や心理に興味がある人です。
なぜユーザーがそのような行動を取るのか、どうすれば満足してもらえるのかを考えることが好きな方は、UXデザインの仕事にやりがいを感じられるはずです。また、論理的思考力も重要で、ユーザーの課題を分析し、データに基づいて解決策を導き出す能力が求められます。
さらに、コミュニケーション能力も欠かせません。UXデザイナーは、エンジニアやマーケティング担当者など、様々な職種の人と協働するため、自分の考えを分かりやすく伝え、相手の意見を理解する力が必要です。
UXデザインの勉強にどのくらいの期間が必要?
UXデザインの習得に必要な期間は、目指すレベルや学習時間によって大きく異なります。
基礎知識を身につけるだけであれば、集中的に学習すれば数ヶ月程度で一通りの概念や手法を理解できるでしょう。
しかし、実務で通用するレベルのスキルを身につけるには、最低でも半年から1年程度の継続的な学習と実践が必要になります。オンラインスクールなどの体系的なカリキュラムを活用すれば、効率的にスキルアップできるため、独学よりも短期間で実務レベルに到達できる可能性が高まります。
UXデザインやWebデザインを学ぶならデジハリ
デジタルハリウッドのオンラインスクールでは、実践的なWebデザインスキルとUXデザインの考え方を同時に学べる講座を提供しています。特に「Webデザイナー講座」は、未経験からプロのWebデザイナーを目指す方に最適なカリキュラムが組まれており、デザインの基礎からHTML/CSS、JavaScriptといった技術面、さらにはUXの基本概念まで幅広くカバーしています。現役クリエイターによる実践的な指導と、質問し放題のサポート体制により、確実にスキルを身につけることが可能です。オンラインで学習できるため、仕事や家事と両立しながら自分のペースで学べる点も大きな魅力です。
まとめ
UXデザインは、単なる見た目の美しさを追求するのではなく、ユーザーがサービスを通じて得る体験全体を設計する重要な取り組みです。ユーザーの課題を深く理解し、データに基づいた設計を行うことで、満足度の高いサービスを生み出すことができます。
UXデザインを学ぶ方法は多様で、書籍やオンライン学習、実践的なプロジェクトを通じて着実にスキルを磨くことが可能です。資格取得も、知識を体系化し専門性を証明する有効な手段となるでしょう。
これからUXデザインを学び、キャリアに活かしたいと考えている方は、まず基礎知識の習得から始め、実践を重ねながら継続的に成長していくことが大切です。デジタル社会において、UXデザインの重要性は今後ますます高まっていくことが予想されます。
この機会にUXデザインの学習をスタートし、新たなキャリアの可能性を広げてみてはいかがでしょうか。


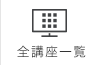
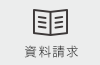
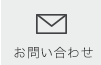
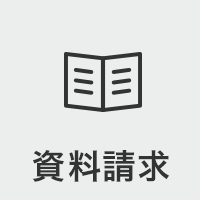











 Webデザイン
Webデザイン




 3DCG・映像
3DCG・映像





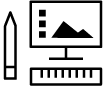 グラフィックデザイン
グラフィックデザイン
 Webマーケティング
Webマーケティング
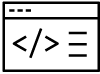 Webプログラミング
Webプログラミング
 アナログスキル
アナログスキル

 その他
その他