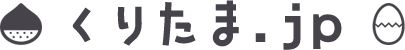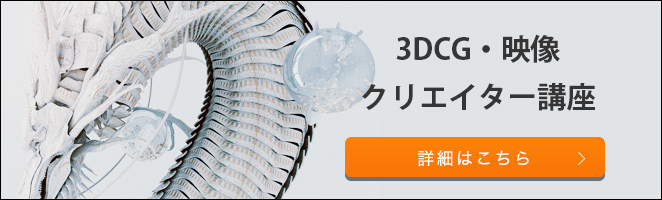3DCGの世界に足を踏み入れようとする際、どのソフトウェアを選ぶべきか悩む方は少なくありません。
特に業界で広く使われているBlenderとMayaは、それぞれに特徴があり、用途や目的によって最適な選択肢が変わってきます。
本記事では、これから3DCGクリエイターを目指す方に向けて、BlenderとMayaの基本的な違い、メリット・デメリット、料金体系を詳しく比較します。自分に合ったソフトウェアを見つけるための判断材料として、ぜひ参考にしてください。
Mayaや3ds Max、映像編集を学びたいあなたにおすすめの講座
Blender(ブレンダー)とは何か
Blenderは、オープンソースの3DCG制作ソフトウェアで、モデリングからアニメーション、レンダリング、合成、モーショントラッキングまで、3D制作工程のほぼすべてをカバーできる総合的なツールです。1994年にオランダのアニメーションスタジオNeoGeoによって開発が始まり、現在はBlender Foundationによって管理・開発が続けられています。
無料で使えることから3DCG初心者の入門ソフトとして人気がありますが、近年では機能の充実や操作性の向上により、プロの現場でも採用が増えています。特に「Blender 2.8」以降のバージョンではUIが大幅に刷新され、より直感的な操作が可能になりました。
「鬼滅の刃」「EVANGELION:3.0(-46h)」など国内外の有名なアニメや映像作品でも取り入れられています。
使用するメリット
Blenderを使用することで得られるメリットは数多くあります。特に初心者からプロまで幅広いユーザーに支持される理由を以下にまとめました。
無料で高機能
Blenderの最大の特徴は、商用利用も含めて完全に無料であることです。3DCGソフトウェアは一般的に高額なものが多い中、Blenderは無料でありながら、モデリング、スカルプティング、アニメーション、シミュレーション、レンダリング、合成、モーショントラッキングなど、3D制作に必要なほぼすべての機能を備えています。
豊富な学習リソース
オープンソースであることから、世界中のユーザーコミュニティが非常に活発です。公式ドキュメントはもちろん、YouTubeやUdemyなどのプラットフォームでは無料・有料問わず膨大な量のチュートリアルが公開されています。また、日本語の解説サイトやフォーラムも多く、日本国内の初心者にとっても学びやすい環境が整っています。
柔軟なカスタマイズ性
Blenderはオープンソースであるため、Pythonを使用したアドオン開発が盛んに行われています。ユーザーの必要に応じて機能を拡張できる柔軟性があり、作業効率を大幅に向上させるアドオンが多数公開されています。
オールインワンのパイプライン
Blender単体で3DCG制作の全工程をカバーできることも大きな強みです。モデリングからテクスチャリング、リギング、アニメーション、シミュレーション、レンダリング、コンポジットまでを一つのソフトウェア内で完結できるため、複数のソフトウェア間でデータをやり取りする手間が省けます。
使用するデメリット
Blenderは多くの優れた機能を持つ一方で、いくつかの課題も存在します。
まず、業界での採用率がMayaなどの商用ソフトと比べるとまだ低い点が挙げられます。特に大手スタジオや企業では、Mayaを中心としたパイプラインが構築されていることが多く、就職や転職を考える場合、Blenderだけでは不十分なケースがあります。
また、独自の操作体系を持っている点も初学者には壁となることがあります。Blender 2.8以降でUIは改善されましたが、他の3DCGソフトからの移行時には操作の違いに戸惑うことがあるでしょう。
さらに、大規模プロジェクトでの安定性や、専門的な分野では、商用ソフトウェアと比較して機能が限定的な場合があります。特にエンタープライズレベルのサポートがないため、商用環境での導入には慎重な判断が必要です。
Mayaや3ds Max、映像編集を学びたいあなたにおすすめの講座
Mayaとは何か
Mayaは、Autodeskが開発・販売している業界標準の3DCGソフトウェアです。1998年に初めてリリースされて以来、映画、テレビ、ゲーム業界で広く採用され、プロフェッショナルな3D制作の現場では欠かせないツールとなっています。
特に、複雑なキャラクターモデリングやリギング、アニメーション、特殊効果などの分野で高い評価を受けており、『アバター』『スター・ウォーズ』『マーベル』シリーズなど多くのハリウッド大作映画の制作に利用されています。
Mayaの最大の特徴は、高度にカスタマイズ可能なワークフローと、MEL(Maya Embedded Language)やPythonによるスクリプティング機能です。これにより、大規模なスタジオでは独自のパイプラインを構築し、複雑なプロジェクトを効率的に管理することができます。
使用するメリット
Mayaを使用する際の主なメリットをいくつか紹介します。
業界標準のワークフロー
Mayaは映画、ゲーム、テレビなどのエンターテインメント業界で最も広く使われている3DCGソフトウェアの一つです。そのため、Mayaのスキルを身につけることは、就職や転職の際に大きなアドバンテージとなります。多くのスタジオでは既存のパイプラインにMayaが組み込まれており、即戦力として活躍できる可能性が高まります。
高度なキャラクターリギングとアニメーション
Mayaはキャラクターリギングとアニメーションの分野で特に優れています。高度な骨格システム、筋肉シミュレーション、表情制御などの機能により、リアルな動きや表情を持つキャラクターを作成できます。Mayaに標準搭載された「Human IK」と呼ばれるキャラクターリギングツールは、モーションキャプチャデータの適用や複雑なキャラクター操作を容易にし、プロのアニメーターから高い評価を得ています。
統合された物理シミュレーション
Mayaには「Bifrost」と呼ばれる強力なプラグインが搭載されており、流体、煙、布、剛体などの複雑なシミュレーションを高い精度で実現できます。また、「nHair」や「nCloth」などの専用シミュレーターも用意されており、髪の毛や衣服の自然な動きを簡単に作成することができます。
使用するデメリット
Mayaを選ぶ際に考慮すべきデメリットについて解説します。
高額な導入コスト
Mayaの最大のデメリットは、その価格設定にあります。Autodeskのサブスクリプションモデルでは、2025年現在、年間28.6万円(月額支払いでは約3.6万円)のコストがかかります。学生や教育機関向けの無料ライセンスは提供されていますが、期間限定であり、商用利用はできません。独立系クリエイターや小規模スタジオにとっては、この導入コストが大きな障壁となることがあります。
なお、デジハリ・オンラインスクールの3DCG講座では、Mayaの無償学生版が使用でき、お得にハイエンドソフトであるMayaの学習ができます。
高い学習曲線と複雑なインターフェース
Mayaは非常に多機能で柔軟性が高い反面、その操作体系は初心者にとって決して直感的とは言えません。UIは機能性を重視して設計されており、初めてMayaに触れるユーザーは膨大なメニューやオプションに圧倒されることがあります。基本的な操作から高度な機能まで習得するには相当な時間と努力が必要です。
3ds Maxとの違いとは
MayaとAutodeskの同じ3DCGソフトウェアである3ds Maxは、しばしば比較されますが、それぞれ得意とする分野が異なります。Mayaはキャラクターアニメーションや映像制作、特殊効果などの分野で強みを発揮し、映画やテレビ業界で広く採用されています。
一方、3ds Maxは建築ビジュアライゼーション、プロダクトデザイン、ゲーム開発などの分野に適しています。
BlenderとMayaの料金の違い
BlenderとMayaは機能面だけでなく、料金体系においても大きな違いがあります。ここでは両ソフトウェアの料金プランを比較します。
※2025-03-31時点での情報です
| ソフトウェア | 個人利用 | 商用利用 | 学生・教育機関 | 更新頻度 |
|---|---|---|---|---|
| Blender | 無料 | 無料 | 無料 | 3-4ヶ月ごと |
| Maya | 年間支払い:286,000円(月ごと支払いより34%お得)
月ごと支払い 月額:36,300円 |
年間支払い:286,000円(月ごと支払いより34%お得)
月ごと支払い 月額:36,300円 |
無料(教育用途のみ) | 年1回+アップデート |
Blenderの料金
Blenderは完全にオープンソースのソフトウェアであり、個人利用・商用利用を問わず、完全に無料で使用することができます。具体的には以下のような特徴があります:
- ライセンス料金: 永久的に無料
- 更新・アップグレード: 無料で定期的に提供(年に3〜4回程度のメジャーアップデート)
- 機能制限: なし(すべての機能が利用可能)
- 商用利用: 制限なし(制作物の著作権は作成者に帰属)
このような料金体系は、特に3DCG学習を始めたばかりの初心者や、予算の限られた個人クリエイター、小規模スタジオにとって大きなメリットとなっています。
Mayaの料金
一方、Autodesk Mayaはサブスクリプション形式での提供となっており、継続的な費用が発生します。Autodeskの公式サイトによると、2025年3月時点での料金は以下の通りです:
- 個人・商用ライセンス: 月額プラン 36,300円(税込)/ 年間プラン 286,000円(税込)
- 学生・教育機関向けライセンス: 教育目的に限り無料(年間更新、利用資格を満たす限り最長4年間)
Mayaはプロフェッショナルな制作環境での使用を想定して設計されており、その価格設定もそれに見合ったものとなっています。大手スタジオや企業にとっては、業界標準のソフトウェアを使用することによる互換性やワークフローの効率化のメリットが、このコストを正当化する要因となっています。
BlenderとMayaどちらを使用するべき?

BlenderとMayaはどちらも優れた3DCGソフトウェアですが、用途や目的によって最適な選択は異なります。
Blenderはこんな人におすすめ
Blenderは以下のような方に特におすすめできます。カジュアルな使用用途な方におすすめといえるでしょう。
- 3DCGを学び始めたばかりの初心者:初期投資なしで高度な3D制作技術を学べます
- 個人クリエイターや小規模チーム:ライセンス料金の負担がなく、単一のソフトウェアで制作工程の大部分をカバーできます
- 予算に制約のある学生やフリーランサー:無料でプロレベルの作品を制作できます
- ゲーム開発者やインディーゲームクリエイター:ゲームエンジンであるUnreal EngineやUnityとの連携が容易です
- YouTubeやSNS向けの3Dコンテンツクリエイター:比較的短期間で習得でき、アニメーションやビジュアルエフェクトなどを手軽に制作できます
Mayaはこんな人におすすめ
一方、Mayaは以下のような方に向いています。将来的にプロのCGクリエイターを目指す方におすすめです。
- 大手スタジオや企業への就職・転職を目指す方:業界標準のツールを使いこなせることが、採用時の大きなアドバンテージとなります
- 映画やテレビのVFX制作に携わりたい方:ハリウッド映画などの大規模制作でよく使用されるツールとワークフローを学べます
- 高度なキャラクターアニメーションを専門にしたい方:プロフェッショナルな現場で評価されているリギングとアニメーションツールを使用できます
Mayaや3ds Max、映像編集を学びたいあなたにおすすめの講座
ソフトの選び方のポイント
3DCGソフトウェアを選ぶ際は、いくつかの重要なポイントを考慮する必要があります。
作りたいもので選ぶ
3DCGソフトウェアを選ぶ上で最も重要なのは、何を作りたいかという点です。
キャラクターアニメーションや映画のVFXを制作したい場合は、これらの分野で業界標準となっているMayaが適しているでしょう。一方、個人制作や小規模チームでのゲームアセット制作、Webコンテンツ、建築ビジュアライゼーションなどを目指す場合は、Blenderの柔軟性と無料という利点が大きな強みとなります。
就職・転職を見据えて選ぶ
キャリアパスを意識してソフトウェアを選ぶことも重要です。3DCG業界での就職や転職を考えている場合は、採用企業が使用しているソフトウェアのスキルを身につけることが大きなアドバンテージとなります。
大手アニメーションスタジオやVFX会社では、Mayaが標準的に使用されているケースが多く、求人情報でもMayaのスキルを求められることが一般的です。一方で、インディーゲーム開発やWebコンテンツ制作、フリーランスの3Dアーティストを目指す場合は、初期投資のかからないBlenderを選択することで、技術習得に集中できるメリットがあります。
理想的には、メインとなるソフトウェアを深く習得しつつ、もう一方のソフトウェアも基本操作程度は身につけておくことで、様々な環境に適応できる汎用性の高いクリエイターを目指すことができます。
3DCGを学ぶならデジハリ

3DCGの技術を体系的に学びたい方には、デジハリ・オンラインスクールの3DCG講座がおすすめです。プロの現場で活躍するクリエイターから直接指導を受けられるカリキュラムで、基礎から応用まで段階的に学ぶことができます。オンライン受講なので、全国どこからでも自分のペースで学習を進められます。
Mayaや3ds Maxだけでなく、After Effectsなど動画編集の基礎についてもわかりやすく習得できる内容となっています。まずは一度講座ページをチェックしてみてください。
まとめ
BlenderとMayaはどちらも優れた3DCGソフトウェアですが、それぞれに特徴があり、用途や目的によって最適な選択肢は変わってきます。Blenderは無料で高機能なオールインワンツールとして、初心者から個人クリエイターに特に支持されています。一方、Mayaは業界標準のソフトウェアとして、プロフェッショナルな現場での採用率が高く、特に就職や転職を見据えている場合は重要なスキルとなります。
料金面ではBlenderの無料というメリットは大きいものの、長期的なキャリアを考えるならば、自分の目指す業界や分野に合わせたソフトウェアを選ぶことが重要です。理想的には、まずBlenderで基礎を学び、必要に応じてMayaにステップアップするという学習パスも効率的でしょう。
どちらのソフトウェアを選ぶにしても、3DCGの基本的な概念や原理は共通していますので、一つのソフトウェアで学んだスキルは他のソフトウェアにも応用できます。大切なのは、自分の目標やキャリアプランに合わせて選択し、継続的に学び続けることです。
デジハリ・オンラインスクールではこれから3DCGや映像を学びたい方に向けた講座をご用意しております。ぜひチェックしてみてください!


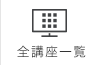
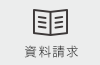
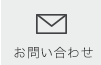
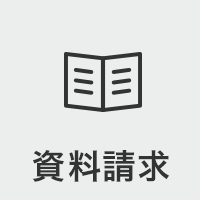











 Webデザイン
Webデザイン




 3DCG・映像
3DCG・映像





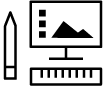 グラフィックデザイン
グラフィックデザイン
 Webマーケティング
Webマーケティング
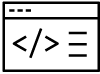 Webプログラミング
Webプログラミング
 アナログスキル
アナログスキル

 その他
その他